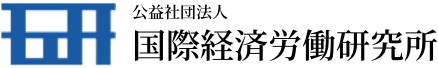機関誌Int
’
lecowk
地球儀 政府・日銀が利上げに踏み切れない理由
(公社)国際経済労働研究所 所長 本山 美彦
世界の豊かな国々は、40年ぶりの大きなインフレに見まわれている。2022年6月末の米国消費者物価上昇率9%弱は、第2次石油危機後のインフレが長期化していた1981年11月以来、40年6か月ぶりの大きさであった。英国も9%強。他のEU諸国も似たような数値であった。超インフレを阻止すべく、世界の中央銀行は政策金利の利上げに踏み切っている。
ヨーロッパ中央銀行(ECB)は、2022年7月、金融引き締めを加速する米・英と歩調を合わせる形で、政策金利を0.5%引き上げるとともに、これまで続けてきたマイナス金利を解除することに決めた。利上げは11年ぶりとなる。
そこに、日本だけが、金融緩和を続けるという姿勢を頑固に崩していない。日本の物価上昇率が世界平均よりもはるかに低いことを政府・日銀は口実にしている。そのために円安が急速に進行しているが、日銀は円安も短期で収束すると強弁している。ただし、物価上昇率は、統計の取り方で大きく異なる。詳しく説明する紙幅はないが、日本の政府統計ほど信用できないものはない。
結論を言おう。日本には利上げに踏み切れない強い理由がある。政府が新型コロナウイルス禍で企業の資金繰りを支援したために、「ゼロゼロ融資」が2021年末で約42兆円と、1年で30%強も伸びた。これでは、わずかな利上げでも、政府は自らの首を絞めることになる。政府の全債務は1千兆円に達している。民間企業も、負債の激増で利上げが命取りになる。
2022.8