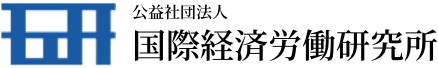機関誌Int
’
lecowk
地球儀 ウクライナの「チェルノゼム」(黒土層)
(公社)国際経済労働研究所 所長 本山 美彦
ウクライナには、「チェルノゼム」(Chernozem)という豊かな黒土層がある。層は、4~16%の「腐植層」(humus)を含んでいる。腐植層は動植物の死骸が分解して生まれた有機物からなる土壌のことである。ウクライナは、国土の68%がチェルノゼム層で、世界のチェルノゼム層の4分の1も占めている。
世界には2つの大チェルノゼム層がある。1つは、ウクライナからロシアに至るユーラシアの「大草原地帯」(the Steppes)。2つは、北米中西部の「グレート・プレーンズ」(the Great Plains)。これは、ロッキー山脈の東側と中央平原の間を南北に広がる台地状の大平原である。
チェルノゼムは、スラブ語の‘cherna’(地球の)と‘zemlya’(土地)との合成語である。チェルノゼムが世界的に有名な用語として使われるようになったのは、ロシアの天才的な地質学者(geologist)のヴァシリー・ドクチャエフ(Vasily Dokuchaev、1846~1903年)が、1883年からこの土壌に関する研究成果を矢継ぎ早に発表するようになってからである。研究論文は、『ロシアのチェロノゼム』(Russian Cheronozem)というタイトルの連作で、ドクチャエフは、これを博士論文のテーマにした。論文は、ロシア各地のチェロノゼム(ロシア語)の共通点と差異点を詳細に記述したものであった。各地の土壌がどのような経緯で形成されたのか、土壌の化学的な成分はどのようなもので、どのような違いがあるのか、それぞれの差異を区分けする基準はどのように求めたら良いのか、こうした手法が、後世の人々によって、「遺伝学的土壌科学」(genetic soil science)と名付けられるようになったものである。
2022.9