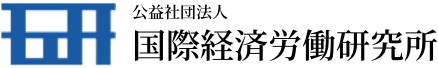機関誌Int
’
lecowk
地球儀 進む種子業界の寡占化
(公社)国際経済労働研究所 所長 本山 美彦
1990年代以降、遺伝子組み換え、ゲノム編集といったバイオ技術が現れた。これらの技術は、それまでよりも、はるかに膨大な研究開発費と、分子生物学や応用化学の高度な知見を必要としたため、それまでの種苗メーカーの手におえるものではなくなった。
それが、「バイオメジャー」と呼ばれる、巨大資本を有する多国籍化学・医薬品企業である。これら巨大企業は、瞬く間に種子業界を席巻した。しかも、メジャーの間で寡占化が急速に進んでいる。
2017年9月、「ダウ・ケミカル」と「デュポン」が合併した。新会社の名称は、「ダウ・デュポン」。この合併で、ダウ・デュポンは世界最大の化学メーカーとなり、この年の売上規模は約860億ドルと桁外れな大きさであった。
ただし、合併後すぐに分社化され、2019年時点で、素材科学の「ダウ」、農業関連の「コルテバ」、特殊化学品の「デュポン」の3社となった。
2018年6月には、農業関連会社として世界最大であった「モンサント」が、「バイエル」によって買収された。買収金額は、660億ドルもの巨額。バイエルは117年続いたモンサントの名前を使わない方針である。モンサントのネガティブなイメージから距離を取ろうとしたのであろう。これで、上位4社の市場占有率は農薬で8割、種子で6割を超えることとなった。4社とは「バイエル」、「コルテバ」、「シンジェンタ」、「リマグラン」である(https://www.sbbit.jp/article/cont1/36568)。
膨大な開発費用をかけても、新製品は模倣されやすい。そのために、業界では、寡占化の進行だけでなく、種苗の知的財産権保護の動きも加速している。こうした事情が、日本の農業法が矢継ぎ早に替えられてきた背景にある。2018年には「種子法」が廃止された。2021年には「改正種苗法」が施行された。
2023.4