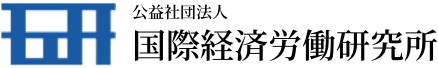機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 史上初のスト決行から約20年
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
日本のプロ野球界で、現在のようなセントラル、パシフィックの2リーグ制が始まったのは1950年だ。この2リーグ制を巡って、プロ野球関係者だけでなく国民的な話題となったのが、約20年前の2004年9月18日、19日のプロ野球史上初のスト決行だった。
昨年12月17日、日本プロ野球選手会が球界再編20周年シンポジウム「ファンも選手も球界の一員です〜あの時何が変わり、何が変わっていないのか」を開催した。プロ野球選手会は労働組合法上の労働組合であり、私も連合時代からおつき合いしていることから、お誘いをいただき参加した。
その発端は2004年6月の大阪近鉄バッファローズとオリックス・ブルーウェーブの合併構想の発覚にさかのぼる。当時、多くの球団オーナーたちは球団経営に頭を悩ませていた。中でも近鉄は大幅な赤字をかかえ観客の入りも多くなかった。そんな状況を打破するため、オーナー側は球団の数を減らし球界全体の赤字を削減しようと考えた。10球団1リーグ制の案もまことしやかに流れた。
当時の選手会長の古田敦也氏は「ファンあっての球界であるが、選手やファンに向けて説明もなく理解を求めることもなく、親会社の都合で赤字が多いからやめる、減らすというのは受け入れることは出来なかった」。また、「選手会としてNPB(日本野球機構)に説明を求めたが、すぐには応じてもらえなかった。これは経営側の問題で選手には関係ないという感じだった。球団が減少すればファンも減る。ファンが減ることは野球選手を目指す子どもたちも減る可能性がある。プロ野球界発展のための球団減少であればみんな納得できるが、その根拠も分からない。選手会としては、せめて1年間ぐらいは合併を凍結して欲しいとも要望した」と振り返った。
合併反対の署名活動では120万人の署名が集まり、オールスターゲームでは全選手が12球団のカラーを織り込んだミサンガをつけてプレーした。東京、大阪では合併反対のファンのデモが起きるなど、プロ野球関係者だけでなく国民的な関心となっていった。
有名になった、巨人の故・渡辺恒雄オーナーの「無礼な、たかが選手が」発言については、「囲み取材である記者に『(オーナーと)直にしゃべった方がいいんじゃないですか』と聞かれて『そうですね』と答えた。それぐらいの程度で。僕が言っているみたいになってるけど。そのあと(記者が)渡辺オーナーに持っていったら、そういう発言をした」と古田氏は明かした。間違いなく、故・渡辺オーナーの発言が、世論の風向きが変わるきっかけになったのは確かだろう。
対話を繰り返すが、両者の溝は埋まらず、最終的に選手会は苦渋の決断としてストライキを決行した。前代未聞のストライキを経て事態は進展し、近鉄とオリックスは合併しオリックス・バッファローズとなり、50年ぶりに新球団の東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生、12球団・2リーグ制は維持された。古田氏は最後に、「今の野球の繁栄はファンをはじめとする関係者のおかげだし、当時のNPB側を動かしたのはファンの皆さんだ」と感謝した。
この球界再編を乗り越え、プロ野球界には様々な変化が起きている。現役選手を対象にした移籍制度「現役ドラフト」、フリーエージェント(FA)制度や代理人の導入など選手会の提言が導入された。NPB以外にも2005年の四国アイランドリーグを皮切りに各地に独立リーグが誕生し、先季はNPBのファームリーグ(2軍公式戦)に新潟と静岡の2球団が新規参入した。12球団の観客数は、先季史上最多を更新した。
20年も経てば、記憶は薄れる。現役の中には、まだ生まれていなかった選手もいるだろう。球界を守るために立ち上がった選手会の先輩たちのことを、ぜひ覚えておいてもらいたい。現在の新入団選手は現行制度が当たり前、しかし、これは選手会が何年も交渉して得てきた権利であり、今の選手たちも選手会に集い球界全体のことを考え、将来の後輩選手のためにという思いで活動して欲しいものだ。
2025.2