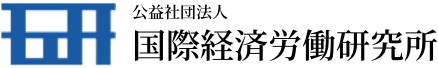機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 ふるさとへの想いと変遷
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
北九州市が2024年に1964年以来60年ぶりに、人口増加を記録した。23年度だけで市内にIT企業が46社進出するなど、雇用創出が順調で20から30代の世代が大幅に改善したという。
市はかつて鉄鋼業の隆盛で79年に県庁所在地の福岡市に抜かれるまで、九州最多の人口を誇る都市であった。鉄鋼業の不振などが影響し、長年人口流出が続き、約107万人をピークに減少に転じ、05年には100万人を割り込んでいる。
このニュースを耳にした時、感慨深いものがあった。加えて、1月下旬の北九州市議会議員選挙で、縁のある後輩が無所属で当選したという嬉しいニュースも飛び込んできた。北九州市は私のふるさとだ。しかし、正確にいえば私は「八幡市」の生まれであり、北九州市という名前になったのは小学校5年生のとき、5市合併によるもの。
63年に門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市が合併して誕生した北九州市。
この合併がなぜ必要だったのか、当時の私には理解できなかった。ただ、周囲の大人たちが語るには、経済発展のため、効率的な都市運営のため、そして地域の一体感を強めるためという理由があったようだ。八幡製鉄所を中心とした産業の発展が、広域的な都市計画とインフラ整備を必要としていたのだろう。関門海峡に面した九州最北端の都市、九州の玄関口として栄えた歴史を持ち、かつての四大工業地帯の一つの北九州工業地帯の中核を担う都市の誕生である。
小さな漁村に過ぎなかった八幡町(後の八幡市)は、1901年に官営八幡製鉄所が開業し、その後日本国内最大の鉄鋼供給地として日本の高度経済成長を支える重要な役割を果たしていた。工場の煙突から立ち上る煙は7色の煙と呼ばれ、まるで街の活気を象徴するかのように空高く伸びていた。学校帰りに友人たちと見上げたその景色は、幼い私の心に強く刻まれている。工場のサイレンが鳴ると、時間の流れを感じ、日常の一部として受けとめていた。
私が19歳より家を出て下宿生活になってから、家族は福岡と北九州市のベッドタウンとして開発された二つのちょうど中間地点の宗像市に転居した。それ以来、故郷の八幡に足を運ぶ機会は次第に減っていき、新しい生活環境に慣れるにつれて、故郷の風景や友人たちの記憶は少しずつ遠のいていった。しかし昨年、北九州市の前市長と意見交換をする機会があり、小倉を訪ねた際にふと思い立って八幡へ足を伸ばした。
かつて賑わっていた商店街は、静寂に包まれ、住宅地へと姿を変えていた。思い出深い小学校は取り壊され、更地となり、そこに立つと風だけが昔の記憶を運んできた。八幡製鉄所と共に繁栄してきたこの街は、高炉の縮小と共に人口も減少し、街並みも大きく変わっていた。それでも、懐かしい場所は心の中に色鮮やかに残っているものだ。
通学路の角、夕方遅くまで友人と遊んだ公園、日一日と成長している自分を実感した中学校の校庭・グランド。何気ない日常の一つひとつが、今では宝物のように思い出される。変わってしまった景色に切なさを覚えつつも、その中に確かに存在していた自分の過去が、温かく迎えてくれるような気がした。
訪れた先で耳にしたのは、地域の新たな取り組みや再生への努力の話だった。地域コミュニティの再生、若者たちの起業支援、観光資源の活用など、変わりゆく街の中でも新しい芽が育っていることを知った。街の変化は寂しさだけでなく、新しい希望も生み出している。
時代の流れと共に街は変わり、人も変わる。しかし、故郷が持つ特別な感情は変わらない。懐かしさと切なさ、そしてほのぼのとした温もりを感じる。その感情は、過去の記憶だけでなく、今を生きる人々との繋がりによっても育まれているのだと実感した。
ふるさとの山に向ひて言ふことなしふるさとの山はありがたきかな(石川啄木)
故郷は、いつでも心の中に生き続けている。その土地に刻まれた記憶と、これからも続く新しい物語が、私たちの心を豊かにしてくれるだろう。
2025.3