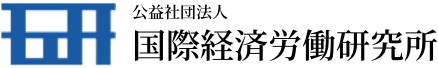機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2022年1月号(通巻1116号)特集概要
1.日本の労働・社会の未来を語る
Contents
〈寄稿〉日本の労働・社会の未来を語る
古賀 伸明(連合総合生活開発研究所 理事長)
本山 美彦(京都大学名誉教授/国際経済労働研究所 所長)
安室 憲一(大阪商業大学・兵庫県立大学 客員教授/国際経済労働研究所 常任理事)
板東 慧(国際経済労働研究所 会長)
2.2021年衆院選をどうみるか
Contents
新川 敏光(京都大学名誉教授/法政大学法学部 教授)
稲増 一憲(関西学院大学社会学部 教授)
野党「共闘」、目指す姿は―韓国政治からの示唆
安 周永(龍谷大学政策学部 准教授)
【調査レポート】
都市圏の候補者によるソーシャルメディア利用
――その実態と効果から課題を考える
山本 耕平(国際経済労働研究所 研究員)
特集1 日本の労働・社会の未来を語る
本誌の新年号では例年、座談会を企画し、中長期的な視点から社会や労働のあり方について議論を行ってきた。今年はコロナ禍であることを踏まえ、座談会は実施せず、古賀伸明氏(連合総合生活開発研究所 理事長)、本山美彦氏(京都大学名誉教授・国際経済労働研究所 所長)、安室憲一氏(兵庫県立大学・大阪商業大学名誉教授・国際経済労働研究所 理事)、板東 慧氏(国際経済労働研究所 会長)に同テーマで寄稿いただいた。
古賀氏は、循環型経済をベースとしたウイズ・ウイルスの社会システムの構築、緊張感ある政治体制の確立、真のすべての働く者の労働運動、という3つの観点から課題の提起および今後への提言を行っている。本山氏は、現代社会を解剖するにあたり、富裕層が金融資産の価格高騰を享受していること、日本の政府債務残高の対GDP比が世界的にも突出していることなど、金融・経済の視点から警鐘を鳴らしている。安室氏は、グローバルな観点から、日本のコロナ対応への成果、今後の世界と経済の課題に言及している。また、今後を考える上で必要な視点として、地球環境改善とCO2削減、自由平等のアピール、個人情報の取り扱いを挙げている。板東氏は、「令和という時代を考える」と題し、21世紀の世界秩序について俯瞰している。
特集2 2021 年衆院選をどうみるか
本特集は、昨年10月に行われた第49回衆議院議員総選挙について、当研究所主催の研究プロジェクト「ポスト動員時代の政治活動研究会」メンバーの研究者の方々から執筆いただいた。様々な角度から総選挙が読み解かれており、今後の運動に資する視点を提供いただいている。執筆者は、新川敏光氏(京都大学名誉教授・法政大学教授、国際経済労働研究所理事)、稲増一憲氏(関西学院大学教授)、安 周永氏(龍谷大学准教授)、山本耕平氏(国際経済労働研究所研究員)である。
新川氏の「2021年総選挙結果を解読する」では、まず自民党、立憲民主党の勝敗について考察し、他に選択肢がなかったために有権者が自公政権を選ばざるを得なかったという状況は民主主義の危機である、と指摘する。さらに、野党共闘の評価、連合の政治的主体性について、過去からの経緯も踏まえながら解説している。最後に、労働組合が歴史的に民主主義の定着に大きな役割を果たしてきたことに言及し、連合の今後に期待するとして締めくくっている。
稲増氏は、「選挙における『敗因の分析』」として執筆いただいた。よく取り上げられる敗因に「マスメディア」があるが、有権者が簡単にマスメディアに流されると考えることは短絡的であるとし、その理由を人間の認知、歴史的出来事を元に解説している。これらを踏まえ、敗因の要因をマスメディアに求めることは次の選挙に向けた改善には繋がりにくいと指摘している。
安氏は、「野党「共闘」、目指す姿は―韓国政治からの示唆」として執筆いただいた。今回の選挙において注目される一つのテーマであった野党共闘について、韓国政治との比較の観点から解説いただいている。日本への示唆として、日本の野党共闘を考える際に、単なる候補者一本化ではなく、支持基盤の拡大とそのための魅力的な政策ビジョンの提示、その上での政党と社会運動団体の間の連携が不可欠であるとする。
山本氏は、「都市圏の候補者によるソーシャルメディア利用――その実態と効果から課題を考える」と題し、調査レポートを執筆いただいた。政治活動におけるソーシャルメディアの利活用は、研究会でも議論に上り、労働組合からの関心も高い。本レポートでは、Twitterのデータを使用して分析を行っている。分析結果から、これからのインターネット選挙との向き合い方を考える上で、オンラインをオフラインの代替ではなく補完ととらえる視点が必要であると述べている。