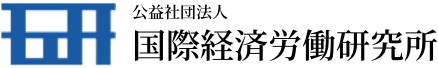機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2022年2月号(通巻1117号)特集概要
2022春闘方針
春季生活闘争(以下、春闘)は、社会の構造的な課題を解決する取り組みであり、労働組合が社会で大きな役割を担う機会といえる。労働組合の諸活動の中でも中心的な位置づけの一つとなっており、本誌でも例年2月号で、春闘方針の特集を企画している。
昨年の2021春闘は、方針検討の段階から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた1年目の春闘であり、連合の春闘方針においても、春闘の意義と目的や基盤整備などが整理され、コロナ禍で春闘に取り組む重要性が確認された。今年の2022春闘は、コロナ禍が継続する中での取り組みであり、様々な社会の歪みも指摘されている。本号では、連合の春闘方針を踏まえ、今春闘を考える上でのポイントについてみていきたい。
特集1は、連合会長・芳野友子氏へのインタビューである。賃上げ、企業内最低賃金、全ての労働者の立場にたった働き方、政策制度要求、ジェンダー平等の推進など、春闘方針のポイントや方針に込めた思いを聞かせていただいた。また、資料として、連合ホームページより、2022春闘方針の「Ⅰ.2022 春季生活闘争の意義と基本スタンス」を抜粋して掲載している。
特集2は、「春闘での労働組合の役割」と題し、高木 郁朗氏(日本女子大学名誉教授)に執筆いただいた。連合の春闘方針を踏まえ、2022春闘や労働組合の役割について、提言いただいている。本稿の中で、「労働組合、とりわけ連合が存在感を発揮するために必要なことは、マクロの立場を明確にし、そのために必要となる手立てを講じ、官製春闘の枠を突破することである」とする。その具体的な手立てとして、連合が中軸となって4つの共闘を組織し、連携していくということが提案されている。4つの共闘とは、第3次産業、中小共闘、地域共闘、女性共闘であり、このようないわば弱者の共闘こそが、今日の日本におけるマクロの賃上げを代表するものとなりうると指摘している。同時に、これまで春闘で重要な役割を演じてきた産別・企業別組合が、さまざまなかたちでこの共闘に協力することへの期待も述べられている。
特集2でも触れられているが、芳野氏は「現場の声に耳を傾けるボトムアップ型」の運動を意識されており、今回のインタビューの発言からも、その思いが随所で感じられる。高木氏は、ここでいう「現場」を、「連合を構成する組合員のみを意味するものではなく、日本の雇用労働者の圧倒的多数を含む中小企業、零細企業、非正規労働者、個人契約で働くいわゆるあいまいな労働者を含む概念であるべきであり、それに退職者や再就職者や、将来仕事につく若者たちをすべて包み込んだ、過去・現在・未来のすべての労働者」を意味すると述べている。2022春闘が、このようマクロレベルでの「現場」を包摂した運動としてどのように展開されるか、注目したい。