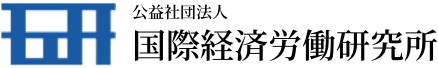機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2022年8月号(通巻1122号)特集概要
2022春闘 成果と今後の課題(前編)
Contents
「新しい資本主義」のもとでの春闘総括はどうあるべきか
高木 郁朗(日本女子大学 名誉教授)
〈産別組織インタビュー〉
JAM
中井 寛哉 氏
基幹労連(日本基幹産業労働組合連合会)
津村 正男 氏
小山 貴史 氏
本誌では、毎年定例的に春闘の成果と今後の課題を特集している。特集は本号および次号の9月号に分けて掲載予定で、本号はその前編である。
2022春闘における連合の方針では、「未来をつくる。みんなでつくる。」をスローガンに掲げ、経済の後追いではなく、経済・社会の活力の原動力となる「人への投資」を積極的に求める「未来づくり春闘」として展開された。連合の「意義と基本スタンス」によると、2022春季生活闘争は、①賃上げ、②働き方の改善、③政策・制度の取り組みを3本柱として、感染症対策をはかりながら景気を安定的に回復させつつ、中期的に分配構造を転換し「働くことを軸とする安心社会」の実現への道を切り拓いていく取り組みと位置付けられている。賃上げに関しては、2014闘争以降、月例賃金の引き上げにこだわり、有期・短時間・契約等の組合員の賃上げがフルタイムで働く組合員の平均を上回るなど、格差是正と「働きの価値に見合った賃金水準」を意識した取り組みが前進しているが、2022春闘では、すべての組合が賃上げに取り組むことを基本に据え、全体の底上げと同時に規模間、雇用形態間、男女間などの格差是正の流れを加速させるとしている。
次号では、この2022春闘の評価と課題について、連合総合政策推進局長・仁平章氏に寄稿いただく予定である。
特集1は、日本女子大学名誉教授 高木郁朗氏による論文「『新しい資本主義』のもとでの春闘総括はどうあるべきか」である。本稿では、春闘が本来どのような意義をもっていたのかを改めて確認しつつ、現在の春闘は、政治の面でも経済の面でも、積極的なカウンターパワーとしての機能を失いつつあるという現状に警鐘を鳴らす。春闘の役割復帰とそれを基盤とする労働組合の存在意義をあらためて示すためにも、大きな歴史的かつ構造的な視点での春闘総括が行なわれることへの期待が述べられている。
特集2以降は産別組織へのインタビューで構成した。今回ご協力いただいた組織は(略称、組織規模順)、UAゼンセン、電機連合、JAM、基幹労連、生保労連、フード連合、サービス連合である。今年も引き続き新型コロナウイルスの影響を考慮し、取材は全てオンラインでの実施となった。本号では、JAM、基幹労連、生保労連の3組織を掲載する。
今回のインタビューでは、①今春闘の方針、②賃金関係・一時金の取り組み、③賃金以外の働き方などに関する取り組み、④中長期的課題をうかがっている。今年は新型コロナウイルスのほかに、ウクライナ問題も少なからず春闘・各産業別組織に影響を及ぼしており、国際情勢の先行きの不透明さが春闘の交渉に影響を与えているところもみられた。また、加えて、多くの産業で人材不足に対する課題意識が聞かれ、人材の確保・定着に注力する取り組みも見られた。アフターコロナ・ポストコロナに向け、労働組合の活動スタイルも柔軟な変化が求められている状況で、今後の春闘のあり方に引き続き注目していきたい。
本特集にあたって、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。