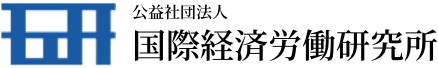機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2022年9月号(通巻1123号)特集概要
2022春闘 成果と今後の課題(後編)
Contents
看護師の賃金と労働組合の取組み
金井 郁(埼玉大学人文社会科学研究科 教授)
2022春季生活闘争を振り返って
仁平 章(日本労働組合総連合会 総合政策推進局長)
〈産別組織インタビュー〉
UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)
古川 大 氏
電機連合(全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会)
中澤 清孝 氏
千葉 淳一 氏
本誌では毎年定例的に春闘の成果と今後の課題を特集している。特集は8月号・9月号の2号にわたる企画であり、本号はその後編である。
特集1では、埼玉大学人文社会科学研究科教授・金井郁氏に、「看護師の賃金と労働組合の取組み」をテーマにご寄稿いただいた。本稿では、日本で看護師の処遇をめぐって、働きかけをおこなう主体の一つである労働組合の取り組みと機能を検討している。労働組合の取り組みとして、医療職を組織化する3組織(UAゼンセン、医労連、自治労)への聞き取り調査を元に考察している。これによると、人事院勧告をもとに賃金が決定される自治労以外の2組織では要求水準は高いものの、妥結額は定昇込みで5000円以下に集中し、多くの病院でベアは実現していない。また、岸田政権が実施する、「看護職員等処遇改善事業」の効果についても確認している。この影響により、妥結額は例年と比べると高いものの、一律的な引き上げにはなっておらず、手当で対応したところも多いことから、この事業が基本給自体を上げることには貢献していないと指摘する。日本の看護師は慢性的に人手不足である中、とくにコロナ禍で感染者の急増期には医療体制がひっ迫し、労働環境の過酷さ等から離職者も増えており、感染者の急増に対する備えはできていない。そこで、労働条件の要求にあたり、必要な時にいつでも医療体制が提供できる環境を整備するという観点を提案している。この「必要性」の観点を踏まえ、医療職を組織化する産別同士で連携し、社会的な労働条件や人員配置の水準を考え、国や病院に働きかけることが必要であると提案している。
特集2では、日本労働組合総連合会(連合)総合政策推進局長・仁平章氏に「2022春季生活闘争を振り返って」と題し、今春闘の特徴と結果を踏まえてご執筆いただいた。今春闘は「未来をつくる。みんなでつくる。」をスローガンに掲げ、連合に集うすべての組織が共闘し賃上げをはじめとする交渉に取り組んだ。「人への投資」と月例賃金にこだわり、「働きの価値に見合った賃金水準」を意識した交渉の結果、労働組合が社会を動かすけん引役としての役割を果たせたと捉えている。平均賃金方式による賃上げ率がコロナ前の水準まで回復したことに加え、中小組合の健闘、短時間等の労働者の賃上げでも成果がみられた。2023春闘の課題として、国際情勢やコロナ禍の動向、輸入物価の上昇、実質賃金の長期低下傾向を踏まえ、働く者の生活の維持・向上のための闘争を進めていくとしている。さらに、企業規模間・雇用形態間・男女間格差の是正に向けた取組みについても継続していく必要があるとしている。
特集3は、産別組織へのインタビューで構成した。本号に掲載しているのは(略称、組織規模順)、UAゼンセン、電機連合、フード連合である。今年の春闘は、全体観としてはコロナ前の賃金改善の水準まで回復しているものの、業種によっては厳しいところもみられる。来年に向けては、賃上げをどのように継続させていくのかが一つの焦点となるといえ、どのような要求・交渉が展開されるか注目される。
前編(8月号)では、日本女子大学名誉教授・高木郁朗氏による論文「『新しい資本主義』のもとでの春闘総括はどうあるべきか」および、産別組織へのインタビュー(JAM、基幹労連、生保労連)を収録しているので、あわせてお読みいただきたい。
この春闘特集にあたり、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。