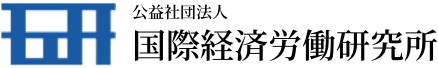機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2022年11/12月号(通巻1125号)特集概要
地域福祉の政策化と地域づくり
――生活困窮者自立支援制度を視野に入れて
Contents
田中 聡子(県立広島大学保健福祉学部 教授)
就労支援を軸とする地域づくり ――相談支援と企業等事業所をつなぐ
小田川 華子((公社)ユニバーサル志縁センター 事務局長)
子どもの貧困対策の現状と課題 ――生活困窮者自立支援との関連を視野に入れて
埋橋 孝文(同志社大学名誉教授)
「地域福祉」は、法制度においては社会福祉法に定められており(注1)、高齢者、障害者、生活困窮者などさまざまな福祉サービスを必要とする人々が、地域を構成するメンバーとして他の住民と同様に社会参加できるようにすることが志向され、これが可能な地域社会をつくること(社会的包摂)が、地域福祉推進の目的とされている。地域福祉をめぐる昨今の動向として、2021年の社会福祉法改正により「重層的支援体制整備事業」が創設されたことが挙げられる。この事業は、市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施するものである。これまでの日本の社会保障制度では、人生において典型的なリスクや課題を想定して、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児童福祉など、属性別・対象者のリスク別の制度を発展させ、専門的な支援を充実させてきた。しかし、一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050問題、介護と育児のダブルケアなど)や、世帯全体が孤立している状態など、従来の支援体制ではケアしきれないケースが発生するようになった。このような中で、地域共生社会(注2)の考え方が打ち出され、市町村が創意工夫をもって包括的な支援体制を円滑に構築・実践できる仕組みをつくるため、この事業が実施されることとなった。社会的な課題の解決や、これからの社会のあり方を考える上で、上記の地域共生社会や、地域福祉は重要な観点の一つだと考えられ、本誌で地域福祉と地域づくりをテーマに特集を企画することとした。なお、本特集の企画にあたり、埋橋孝文氏(同志社大学名誉教授、特集3執筆)にご協力いただいた。記して感謝申し上げたい。
特集1は、田中聡子氏(県立広島大学教授)に「地域福祉の拡大と政策化の系譜」と題してご執筆いただいた。はじめに、日本における戦後の社会福祉政策の歴史を概観し、社会福祉が貧困対策から生活課題へとシフトし、関連領域との連携により拡大する中で、地域福祉がどのような背景で登場し位置付けられていくのかを確認している。次に、地域福祉がどのように拡大し、政策として形成されていくのかについて、厚生白書(1990年~2000年)と厚生労働白書(2001年~2021年)を用いて考察し、地域で生活するうえでの様々なニーズに対してその対象や役割が拡大・多様化する過程を明らかにしている。さらに、地域福祉計画の守備範囲の拡大についても検討を加えている。このよ うな考察を踏まえ、これまで地域住民が担ってきた活動が地域福祉計画に導入されることにより、昨今の地域包括ケアシステムの互助活動や重層的支援体制整備事業にどれくらい住民の意思が反映されているかが不明であること、政策目標が数値として具体化されないために評価が難しいという課題を指摘し、基礎的な地域福祉計画の具体的な項目の精査による実態把握、地域共生社会の政策評価など、今後の研究の着眼点にも言及している。
特集2は、公益社団法人ユニバーサル志縁センター事務局長の小田川華子氏に、「就労支援を軸にした地域づくり」についてご執筆いただいた。就労支援は、相談に続く体験や訓練、雇用など様々な段階で企業等事業所の協力、連携がなくてはなりたたないが、その連携の仕組みが不十分であるために、就労支援がうまく機能しないという課題があると指摘し、就労にまつわる課題と政策は、福祉のみならず、雇用、地域経済、地方創生の領域からも検討すべきテーマであるとする。そこで今回の論文では、就労支援は相談者に寄り添った個別の支援が必要であるとしつつ、個別支援そのものではなく、個別支援をより充実させるための地域づくりに焦点を当て、相談支援と企業等事業所をつなぐ仕組みや、その運営を担うアクターについて、事例を元に整理している。はじめに、就労支援のニーズにたいして、高齢者、障害者などといった対象領域ごとではなく、「未活用労働力人口」(働きたいが働けていない、あるいはもう少し働きたいと考えている人)といった、これまで支援してきた層に加えて幅広い層も視野に入れた検討の必要性を述べている。続いて、就労支援を軸にした地域づくりの重要なステークホルダーである企業等事業所の課題を整理し、慢性的な人手不足、早期離職、定着率の上昇、インターンシップのコストなどを挙げている。また、農業等一次産業においても、従事者の確保、育成を就労支援の一環で行うことも可能であるとし、その仕組みや考え方が述べられている。さらに、生活困窮者自立支援機関でこれまでに取り組まれできた試みをとらえ、生活相談、就労支援、地域活動支援を統合的に実施している事例(東京都小平市、長野県東御市)、無料職業紹介を活用した雇用マッチングの事例(兵庫県尼崎市)を紹介し考察をおこなっている。社会福祉政策全体において重層的な支援体制の整備が求められている状況を踏まえ、就労支援を軸にした地域づくりの事例が、相談者の希望や状況に沿った丁寧な支援を支える仕組みとして、他の地域においても参考になるとしている。
特集3は、埋橋孝文氏(同志社大学名誉教授)に「子どもの貧困対策の現状と課題」について、生活困窮者自立支援との関連を視野に入れてご執筆いただいた。まず、貧困と対策の推移を概観し、貧困率は漸減傾向がみられるものの、子どもの貧困にかんする指標は、この貧困率に代表されるようなアウトカム(活動によってもたらされた結果)指標がほとんどであり、関係施策の実施状況や対策の効果が検証可能なものになっていないこと、政策のアクティビティやアウトプット(活動や活動によって生み出されたもの)指標が極めて少ないことを指摘している。そのため、新しい指標の設定、なかでも生活困窮者支援に関わる指標の追加を提案している。また、子どもの貧困対策に関連する省庁(事務局の内閣府、具体的な施策を担当する文部科学省と厚生労働省)の連携がはかられていないことも問題としている。次に、生困法下での施策は子どもの貧困に大きく関係することから、社会保障審議会の議事録を元に、子どもの学習・生活支援事業をめぐる論点を確認している。最後に、埋橋氏も携わってこられた、さまざまな困難を抱えた子どもたちが安心して過ごせる居場所で生き抜く力を育むことを目標に展開されている「子ども第三の居場所」事業(日本財団)が、子どもの貧困対策や、生活困窮者自立支援政策に対してどのような示唆をもたらすのかを検討している。2018年の生困法改正によって、子どもの学習のみならず生活も含む支援が目指されるようになったが、日本財団の事業は子どもの生活支援を超えて保護者自身の困りごとなどへの支援にも及んでいるという。事業での調査研究によって①子どもの自己肯定感の醸成が肝要であること、②保護者への生活支援が子どもの生活習慣や自己肯定感に好影響を与えることが立証されており、今後の支援や居場所事業にも参考になるとしている。
注釈
注1「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように地域福祉の推進に努めていかなければならない」と定められている(社会福祉法第4条)。
注2 地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことをいう。
(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)