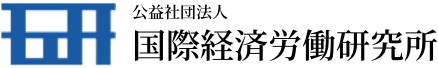機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2023年7月号(通巻1131号)特集概要
最低賃金を考える
Contents
現在わが国における最低賃金制度の課題と展望
藤田 安一(とっとり地域自治研究所 理事長・鳥取大学名誉教授)
〔労働組合役員と研究者による対談〕最低賃金をとりまく諸課題と影響
齋藤 隆志 氏(明治学院大学経済学部教授)
※労働組合役員の方は匿名にて掲載
最低賃金法の主旨を踏まえれば、最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することで労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定と、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保を目的とするものであるといえる。地域別最低賃金は近年上昇傾向にあり、直近(2022年10月)の改定では、過去最大の引き上げ幅となる31円プラスの961円(全国加重平均)となっている。一方、実質賃金は伸び悩み、物価の上昇で多くの労働者の生活は苦しくなっている。
今年の2023年春闘では、物価上昇を背景に例年以上の要求額を示し、大幅な賃金改善を獲得した労働組合も少なくない。しかし、最低賃金近傍の水準で働く人びとの大多数は労働組合に加入しておらず、春闘による賃上げの効果が届きづらいのが現状である。すでに最低賃金の問題に力を入れて取り組んでいる労組もあるが、組織化されていない労働者も含めた社会全体の賃金を上げるには、最低賃金そのものの引き上げが不可欠であり、セーフティネットとしての最低賃金の役割・意義を再考する必要性が生じている。
このような背景を踏まえ、本号で最低賃金にかんする特集を企画することとした。本特集は、最低賃金決定の過程にかかわられた経験をおもちの専門家による寄稿、および労働組合役員と研究者による対談の2本立てで構成した。
特集1は「現在わが国における最低賃金制度の課題と展望」と題し、鳥取大学名誉教授でとっとり地域自治研究所理事長の藤田安一氏にご執筆いただいた。藤田氏は、鳥取地方最低賃金審議会の元会長であり、審議過程の全面公開を中心に最賃審議会の運営に民主的ルール(鳥取方式)を導入した方である。この論文では、「最低賃金の水準」「最低賃金の決定方式」「最低賃金審議会の運営方法」の3つの観点から、最低賃金の現状と問題点、およびその改革方向について検討している。まず、「最低賃金の水準」について、日本における現行の最低賃金水準では将来や不測の事態に備えた貯蓄が十分にできず、諸外国と比較しても、その水準が低いことを指摘する。最低賃金額の引き上げは喫緊の課題であると同時に、引上げが困難な中小零細企業を支えるための視点も提示している。次に、「最低賃金の決定方式」では、どのような方法で最低賃金を決めるのが適切なのかについて検討している。全労連の調査によれば、最低生計費に地域差はほとんどなく、それゆえ全国一律の最低賃金制度の導入が適切であると主張する。最後に、「最低賃金審議会の運営方法」について、鳥取地方最低賃金審議会でおこなわれた、審議会の全面公開の実現、水面下の交渉の禁止、意見聴取を(紙面ではなく)直接おこなうようにするなどの改革を紹介しつつ、民主的な審議会運営への提言をおこなっている。加えて、審議会の構成メンバーの多様化の必要性も改革の課題であると述べている。
特集2は、実際に最低賃金の議論にかかわってこられた労働組合役員の方の意見も反映したいと考え、研究者との対談のかたちで収録した。この対談には、労働経済学が専門で、研究所の研究会等にもかかわっていただいている、齋藤隆志教授(明治学院大学経済学部)にご参加いただいた。なお、組合役員の方は匿名でご参加いただいた。