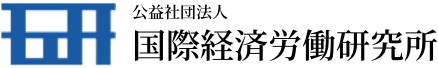機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2023年8月号(通巻1132号)特集概要
2023春闘 成果と今後の課題(前編)
Contents
春闘の意義と今後の課題 ―2023年を真の転換点とするために―
玄田 有史(東京大学社会科学研究所 教授)
〈産別組織インタビュー〉
UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)
古川 大 氏
電機連合(全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会)
中澤 清孝 氏
情報労連(情報産業労働組合連合会)
北野 眞一 氏
航空連合
又吉 謙 氏
本誌では、毎年定例的に春闘の成果と今後の課題を特集している。特集は本号および次号(9月号)の2号連続で掲載予定であり、本号はその前編である。
90年代後半から続く慢性的なデフレに加え、エネルギー価格の高騰などによる急性インフレも重なり、家計においては賃金が物価上昇に追いつかず、企業部門においては適切な価格転嫁が進まないなどの問題を背景に、労働者の生活が一層厳しさを増すなか、賃上げへの社会的な期待も高まっていた。連合の2023春闘方針では「くらしをまもり、未来をつくる。」をスローガンとし、短期的な視点のみならず、中期的・マクロ的視点からも社会全体で問題意識の共有に努め、GDPも賃金も物価も安定的に上昇する経済へとステージを変える転換点とすることが示された。
連合の最終まとめ(2023年7月21日)では、連合が賃上げに改めて取り組んだ2014年以来最高かつほぼ30年ぶりとなる水準の賃上げが実現したと評価している。一方、実質賃金の向上という点では課題が残り、今年の賃上げの流れを来年以降も継続していくことが不可欠であるとしている。そのためには、中小企業や状況が厳しい産業においても適正な価格転嫁を実現できるような環境の整備が必要であると述べられている。2023春闘の評価と課題の詳細については、次号で連合総合政策推進局長・仁平章氏に寄稿いただく予定である。
本号の特集1は、東京大学社会学研究所教授・玄田有史氏による論文「春闘の意義と今後の課題―2023年を真の転換点とするために―」である。まず、2023春闘について、連合のまとめを踏まえて「一部で課題は残しつつも、全般的には一定の成果を上げた」と評価しつつ、労働者の持続的な生活改善には、この流れを継続させる必要があり、そのためにも春闘における交渉が重要であることが再確認された、としている。次に、春闘のような交渉の意義について、ハーシュマンの理論を引用して考察している。ハーシュマンは、組織の衰退を回避するための方策の一つとして「離脱」機会の確保を挙げているが、この離脱だけではない別の仕組みが必要であるとし、「発言(ヴォイス)」の重要性を指摘している。玄田氏は、「春闘には、今後も発言による労使の合意形成が、組織と構成員の改善につながることを明らかにする、きわめて重大な意義がある」と述べている。また、実質賃金の改善に向けては、労働者の実質賃金が確保されなければならないという社会的合意を積み重ねていくことの意義に触れ、そのためにも、労働者が直面している物価水準がどのような状況にあるのか等、「実質」に関するより詳細なデータに基づく交渉や議論が、今後いっそう盛り上がることを期待したいとしている。最後に、マクロの視点より、春闘と最低賃金の交互作用について考察している。マクロ経済に及ぼす最低賃金の影響が大きくなるなか、今年に限らず、春闘の結果が最低賃金にも適切に反映される流れが定着していけば、春闘の持つマクロ的な意味合いは、さらに大きくなっていくだろうと指摘する。春闘と最低賃金の交互作用を通じて、適切な労使交渉のあり方がマクロ経済にも反映されるという、あるべき労働市場の姿が今後構築されていくことへの期待を寄せている。
特集2以降は産別組織へのインタビューで構成している。今回ご協力いただいた組織は、UAゼンセン、電機連合、JAM、情報労連、フード連合、航空連合、交通労連、サービス連合(略称、組織規模順)の8組織で、本号は、UAゼンセン、電機連合、情報労連、航空連合の4組織の記事を掲載している。また、コロナの影響がとくに大きかった産業における春闘を考えるという観点から、今年は新たに航空連合と交通労連にお話をうかがった。
今回のインタビューでは、おもに①2023春闘の方針、②賃金関係の取り組み、③賃金以外の働き方などに関する取り組み、④2024春闘の展望・中長期的課題などをうかがっている。今年は、ほとんどの組織で賃上げが重点的な取り組みと位置づけられていたが、高齢者雇用やリスキリング、格差是正に向けた取り組みなど、独自にお話しいただいたトピックもある。加えて、多くの産業で人材不足に対する課題意識も聞かれた。2024春闘以降も継続的な「人への投資」や適正な価格転嫁が求められるなか、春闘をめぐる動向に引き続き注目していきたい。
本特集にあたって、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。