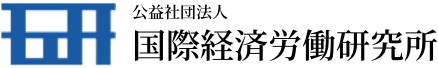機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2023年9月号(通巻1133号)特集概要
2023春闘 成果と今後の課題(後編)
Contents
金井 郁(埼玉大学人文社会科学研究科 教授)
李 旼珍(立教大学社会学部 教授)
仁平 章(日本労働組合総連合会 総合政策推進局長)
〈産別組織インタビュー〉
JAM
中井 寛哉 氏
フード連合(日本食品関連産業労働組合総連合会)
千葉 淳一 氏
交通労連(全国交通運輸労働組合総連合)
佐々木 弘臣 氏
サービス連合(サービス・ツーリズム産業労働組合連合会)
石川 聡一郎 氏
本誌では、毎年定例的に春闘の成果と今後の課題を特集している。特集は8月号および9月号にわたる企画であり、本号はその後編である。
特集1は、金井郁氏(埼玉大学人文社会科学研究科教授)による「インフレ下の春闘 ―非正規労働者の賃金に注目して」である。2023春闘は、30年ぶりの高水準での妥結となったが、物価上昇により自動的に賃金が上がるわけではなく、賃上げ交渉の結果として賃上げは実現される。そこで、連合傘下のなかでも要求額・妥結額が相対的に高かったUAゼンセンと、同組織の賃上げを先導したオールサンデーユニオン、すかいらーく労働組合の春闘のスケジュール、方針決定、賃上げに向けた取り組み、妥結状況を近年と比較して考察している。それをもとに、非正規雇用労働者の賃上げ率が時給ベースで正社員を上回るということがどういうことなのか、また、雇用形態間格差の是正をいかに考えるべきかを検討している。まず、UAゼンセンの今次春闘の特徴として、例年にない高水準の要求・妥結金額になったこと、中小企業にも賃上げが波及したことの2点を挙げ、率ではパートタイム組合員が正社員組合員よりも高い妥結となったことを挙げている。オールサンデーユニオンは3年連続で純ベアを要求してきたが、今年は早めの妥結が地域の相場形成につながるという会社側の意向もあり、高水準での妥結を早期に達成した。すかいらーく労働組合は、賃上げの必要性について組合役員や会社側の理解を得るため、産別や他組合から収集した情報が役に立った。これらの事例より、今次春闘で「集団的な賃上げ交渉の重要性が改めて確認された」とする一方、非正規労働者の間の賃金序列のひずみへの懸念も課題として示されている。また、正社員と非正社員の処遇格差についても、賃金制度の構築などを検討すべきだとしている。
特集2は、李旼珍氏(立教大学社会学部教授)による「企業規模間賃金格差の是正に向けた労働組合の取り組みと課題」である。春闘で企業規模間格差を是正する方策のひとつに、中小企業の賃上げが大企業を上回るか同水準の状態を維持することを挙げる。それには産別の関わり方が重要になるとし、中小組合の賃金交渉支援について、JAMと基幹労連の事例から検討している。JAMでは組合規模間の賃上げ額の差が縮小傾向にあり、地方JAMによる個別単組の闘争支援が小規模組合の賃上げを後押しするとしている。次に、基幹労連の取り組みとして、単組の経営者に労働条件などの改善を要請する「経営要請行動」を挙げ、その効果を評価している。続いて、大手組合の賃上げが小規模組合の賃上げにどの程度波及しているかについても検討を加え、賃上げ額の高位平準化をもたらす春闘相場を波及させるためには、より多くの産業別組合や企業連・グループ労連が中小組合の賃金闘争支援に取り組む必要があるとしている。
特集3は、連合総合政策推進局長の仁平章氏による、2023春季生活闘争の振り返りである。今春闘では「くらしをまもり、未来をつくる。」をスローガンに掲げ、「デフレマインド」からの脱却のために、賃上げと適切な価格転嫁を進める必要性を主張した。賃金改善分獲得が明らかな組合において、比較可能な 2013闘争以降で妥結組合数・割合ともに最も高い数字となり、平均賃金方式による賃上げ率は全体平均で3.58%となった。30年ぶりの高水準を引き出した2023年春闘は、未来につながる転換点となり得るものだったと評価している。今後の課題に「人への投資」と月例賃金改善の継続、付加価値の適正分配の取り組み強化、社会対話の推進などを挙げ、多様な働く仲間を包括した集団的労使関係の拡大をめざすとしている。
特集4は、前号に引き続き、産別組織へのインタビューで構成した。本号は、JAM、フード連合、交通労連、サービス連合の4組織(略称、組織規模順)を掲載している。
前号には、玄田有史氏による論考と、UAゼンセン、電機連合、情報労連、航空連合のインタビューを収録しているので、あわせてお読みいただきたい。
本特集にあたり、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。