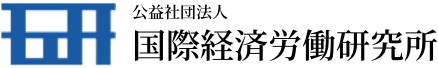機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2025年3月号(通巻1148号)特集概要
鎧を隠した袈裟を正しく見てこなかったことへの反省
本号の特集は、当研究所所長の本山美彦氏による論稿を収録している。本山氏は世界経済論を専門とし、米国主導の「グローバリズム」のいかがわしさを指摘する一方で、同国の世界戦略や、対日経済圧力の実態などの問題点の解明を行ってきた1。また、当研究所が主催する研究プロジェクトの主査も歴任し、代表的なものとして「日本型企業統治」研究PJ(2003~04年)、「日本の強み・弱み―その『仕分け』」研究PJ(2011~14年)、「AI社会に生きる」研究PJ(2018~21年)等がある2。
本稿は、昨今の日本の経済状況に関する問題提起を目的とするものである。日本の『平家物語』の「鎧の下の袈裟」になぞらえ、これからの「希望の灯」となることを願って執筆されている。
2024年に実施された第57回アメリカ大統領選挙では、共和党のトランプ氏が民主党のハリス氏を破り勝利した。トランプ氏が大統領就任前に発言3した、「グリーンランドを米国領にする」等の内容や、関税率の大幅な引き上げについて、本山氏は本稿の冒頭で、「自由市場、自由貿易、個人の自由」という“袈裟”を脱ぎ捨てたことの表れであり、“袈裟”そのものが単なる「絵空事」であったことを示している、と指摘する。なお、本稿での“鎧”は国家の利権と大統領権限の意味で用いられている。
各節の概要は以下のとおりである。
Ⅰ 見かけの袈裟を批判し、国家介入という鎧の必要性に気付いたジェイコブ・ヴァイナー
ヴァイナーは新古典派経済学の主導者とみなされ、自由貿易論を確立したとされる。新古典派経済学は、「国家が介入するのではなく、市場経済に委ねる」という考え方であるが、ヴァイナーは国際的な権威による管理の必要性を示唆し、また、それぞれの時代に応じた関税同盟の必要性を至る所で述べていた。
Ⅱ 国家による市場介入を否定していたはずのリバタリアンたち
リバタリアンは、国家や政府の干渉に強く反対し、個人の権利と自己責任を重視することを信条としている。名うてのリバタリアンであるピーター・ティール氏がトランプ氏を支持し、同様にリバタリアンであるコーク兄弟は自身の財団(コーク財団)をつうじて知識人やシンクタンクに投資し、政策にも大きく関与している。トランプ氏もこのコーク財団に取り込まれていることを指摘する。
Ⅲ コーク財団による大学への寄付の急増によって芽生え始めた「反コーク運動」
アメリカでは、コーク財団による大学への介入にたいして、「コーク財団に反対し、私たちのキャンパスを護ろう」という「UnKoch My Campus」という全国組織が生まれている。この「反コーク運動」の萌芽的な動きを紹介している。
最後に、「真の自由とは何か」について考えることの重要性を述べ、それが広く行われることへの期待を込めて論稿をとじている。
1 その成果は、『ESOP ―株価資本主義の克服』(シュプリンガー・ジャパン、2003年)、『売られ続ける日本、買い漁るアメリカ― 米国の対日改造プログラムと消える未来―』(ビジネス社、2006年)、『金融権力―グローバル経済とリスク・ビジネス― 』(岩波書店、2008年)などにまとめられている。
2 研究PJに関連する著書として、『アソシエの経済学―共生社会を目指す日本の強みと弱み』(社会評論社、2014年)、『人工知能と21世紀の資本主義―サイバー空間と新自由主義』(明石書店、2015年)、『人工頭脳と株価資本主義― AI投機は何をもたらすか』(明石書店、2018年)がある。また、近著として『「協同労働」が拓く社会―サステナブルな平和を目指して』(文眞堂、2022年)がある。
3 トランプ大統領は就任初日の1月20日、「米国第一の通商政策」と題する大統領覚書を発表し、広範な通商分野の調査を関係省庁に指示した。報告期限はほとんどが4月1日までと設定されており、それまでは追加関税などの貿易制限措置は導入されないとみられる。(https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/01/7f2d164e566b50cb.html)